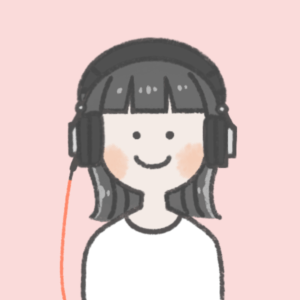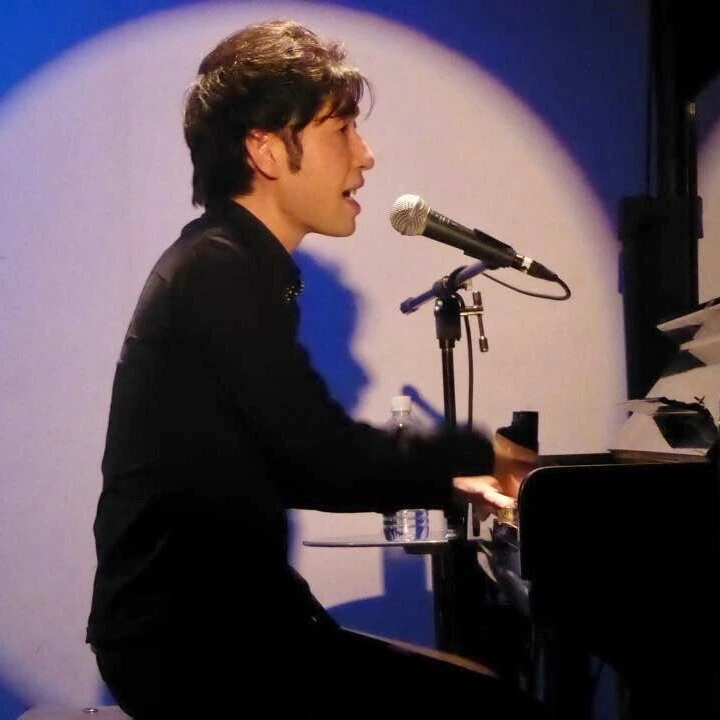【PR】DAW・プラグイン・機材はサウンドハウス
曲の構成を作ろう|Aメロ・Bメロ・サビのつながりで1曲に仕上げる方法
「VOCALOID(ボーカロイド)」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。
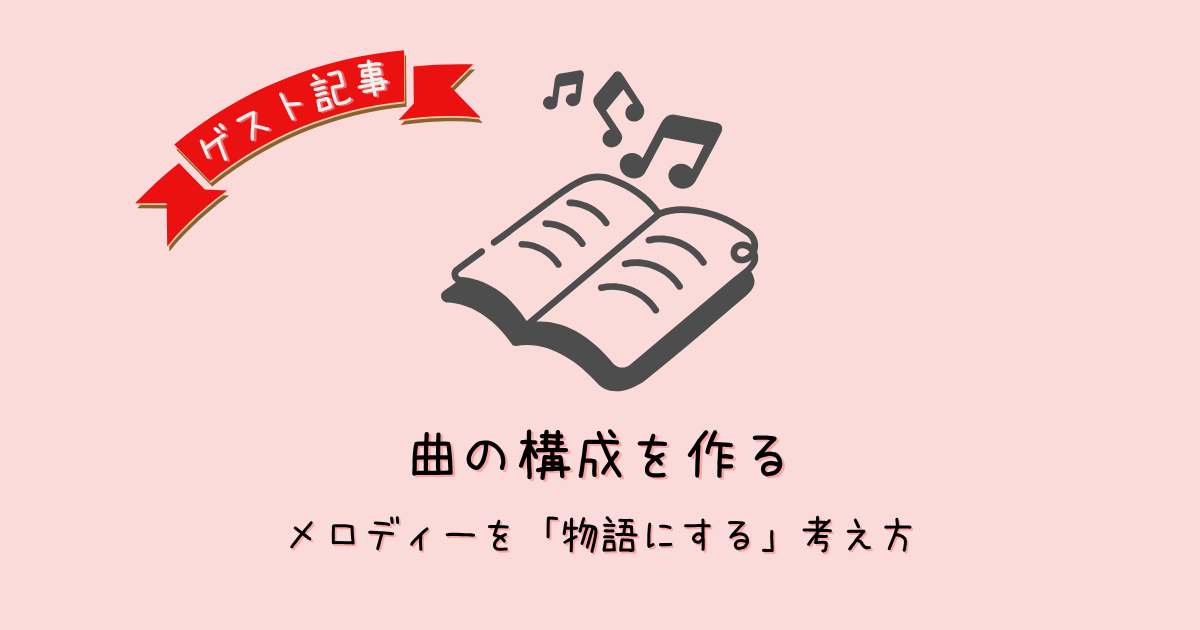
前回の記事では、鼻歌からメロディを作り、アイデアを録音してストックするところまで紹介しました。
 管理人
管理人「最初から曲の一部として作り始めるより、気軽にワンフレーズをアイデアとして録音していく」というアプローチでした。
今回は、その次のステップ。「録りためたメロディを組み合わせて、1曲として形にする」段階です。
ここで多くの初心者がつまずくのが、“どこから手をつければいいか分からない”という点。
Aメロ、Bメロ、サビなど、曲の各部分のそれぞれの役割やつながりを理解しておくと、曲の流れを自然に作ることができます。
最初は「サビができたけど他が続かない」という壁にぶつかると思います。でも、AメロやBメロにはそれぞれサビを引き立てる役割があります。そこを意識するだけで曲のまとまり方が変わります。
曲を構成する4つのパートの役割
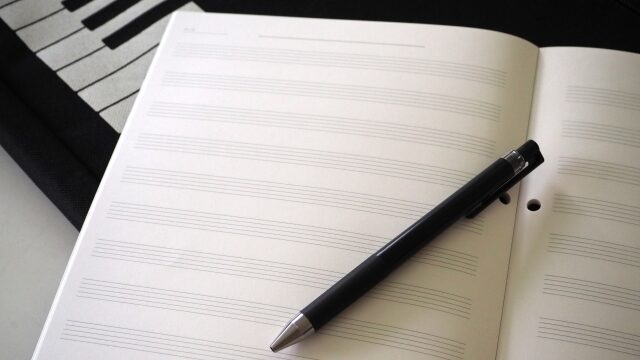
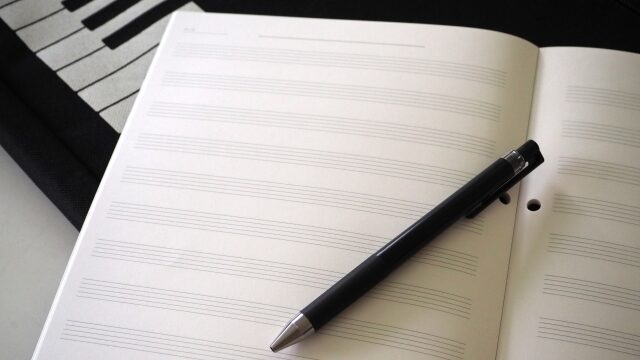
1曲は一般的に、Aメロ → Bメロ → サビ(→ Cメロ)という流れで構成されます。
それぞれには、明確な“役割”があります。
| Aメロ | 物語の始まり。曲の世界観や雰囲気を伝えるパート。 |
|---|---|
| Bメロ | サビへの助走。少し盛り上がりをつけて、サビへの期待を作る。 |
| サビ | 感情のピーク。曲のテーマを最も強く表現する部分。 |
| Cメロ | (あれば)曲の中盤で変化を加えるパート。飽きさせないための“景色替え”の役割。 |
Aメロで感情を“語り始め”、Bメロで“動かし”、サビで“爆発させる”イメージです。
各パートを作るための考え方


役割を確認したところで、Aメロ・Bメロ・サビ・Cメロのそれぞれを作るときの考え方を紹介します。
Aメロを作るときの考え方|「静かさ」で聴き手を引き込む
Aメロは曲の入口であり、聴き手を引き込む大事な部分です。
Aメロはサビと対になる存在です。
サビが感情のピークだとすれば、Aメロは“サビの前の静けさ”を描く場所。
音域をサビより少し低めに、リズムも抑えめにすると、自然に緩急がつきます。
たとえば、サビが高音で勢いのある曲なら、Aメロは落ち着いた低音域で始めてみましょう。メロディラインが単調でも構いません。むしろ「静かさ」がサビのインパクトを引き立てます。
僕はAメロを“語るように歌う”ことを意識しています。リズムを詰めすぎず、言葉を置くようにメロディを作ると自然に“歌心”が出てきます。
Bメロを作るときの考え方|「溜め」でサビへの橋渡し
BメロはAメロからサビへ“橋渡し”するパートで、曲全体の流れを決める要です。
Bメロでは、音域を少しずつ上げていくと、自然に盛り上がりが生まれます。また、Aメロよりリズムを細かくしたり、コード進行を動かすことで“変化”を作るのも効果的です。
印象的な「キメ」や短いリズムフレーズを入れると、サビへの期待が高まります。
Bメロでの“溜め”があると、サビがより強く響きます。あえてサビ直前を静かにするのもひとつの演出です。
サビを作るときの考え方|覚えやすいメロディーで心をつかむ
サビは曲の“核”です。
聴き手の印象を決める最も重要なパートなので、音域・リズム・言葉のすべてに“覚えやすさ”を意識しましょう。
おすすめは、短いメロディの繰り返しです。
「ラララ~」でもいいので、自然に口ずさめるフレーズを中心に構成します。
音域はAメロ・Bメロよりも高く、歌のピークとなるようにします。
僕はサビの最初に“印象的な一音”を置くようにしています。1小節目の頭をどう始めるかで、聴き手の心をつかめるかが決まると思っています。
Cメロを作るときの考え方|雰囲気を変えてドラマチックに
Cメロは必須ではありませんが、曲の後半に“変化”を与えるためのパートです。全体の長さや構成によって入れる・入れないを決めましょう。
Cメロを作るときは、Aメロやサビとは異なるコード進行やリズムを使うのがおすすめです。
少し雰囲気を変えることで、曲全体のドラマ性が高まります。
Cメロでは“違う景色を見せる”気持ちで書きます。たとえば転調やブレイクを入れても面白いです。
曲の流れを作る!各パートの組み立ての考え方


Aメロ・Bメロ・サビを作ったら、それぞれを“どう繋ぐか”を意識しましょう。
曲の流れを作る考え方
曲を通して自然な流れを作るためには、音域の上昇と感情の流れを一致させるのがポイントです。
また、将来的に編曲(アレンジ)をすることを考えながら作ると、構成が整理しやすくなります。たとえばAメロでは伴奏を減らし、Bメロで楽器を増やして、サビで一気に開放する。
このイメージを持つだけで、メロディの作り方にも説得力が出てきます。
“どこで楽器を増やすか”をイメージすると、自然とメロディの強弱も付けやすくなります。作曲と編曲は、実は密接に繋がっています。
イントロ・間奏・アウトロの考え方
曲の構成を完成させる上で、イントロやアウトロも大切な要素です。曲の世界観を印象づけたり、ライブでの流れを作ったりする効果があります。
| イントロ | 2〜4小節程度の短いフレーズでOK。サビやAメロのモチーフを引用すると統一感が出ます。 |
|---|---|
| 間奏 | サビの後などに配置。ボーカルが休む時間を作りつつ、楽器のアレンジを活かします。 |
| アウトロ | 曲の締めくくり。イントロと同じフレーズを繰り返すと“余韻”が生まれます。 |
アウトロを作るときは、“曲が終わっても心に残る一音”を意識しています。静かに終わるのも、フェードアウトするのも素敵です。
まとめ|録音したアイデアを“物語”にする


ここまでの内容を整理すると、曲作りはまるでストーリーを紡ぐような作業です。
録りためた小さな鼻歌も、この流れを意識して繋げるだけで“ひとつの作品”に変わります。
作曲はパズルみたいなものです。ピースをはめていくうちに、気づけば1曲になっている。焦らず、一つひとつのフレーズを育ててみてください。